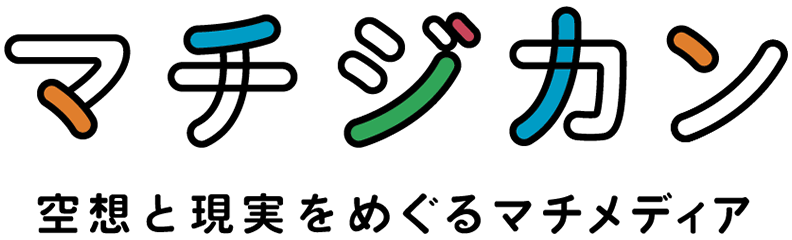「自分が住むまちにこんな施設があったらうれしいな」
そんな思いが具現化したような文化・子育て公共複合施設「おにクル」が2023年11月、大阪府茨木市に誕生しました。
オープンから約1年で来館者数200万人を突破。人口28.5万人、大阪の摂津地方に位置し、利便性と自然豊かな環境を併せ持つベッドタウンでこのペースは驚異的ともいえます。取材した当日も、平日の午前中でありながら多くの市民がおにクルでくつろいでいたのが印象的でした。
また、日本デザイン振興会が主催する「2024年度グッドデザイン賞」でグッドデザイン・ベスト100、「みんなの建築大賞2025」では大賞と推薦委員会ベスト1位をW受賞するなど、市民だけでなく日本中が注目する公共複合施設となっています。
茨木市に暮らす人々にとって必要とされ、公共施設として注目を集める「おにクル」は、どのように設計されたのでしょうか。
「おにクル」を伊東豊雄建築設計事務所と共同設計した竹中工務店の市川雅也さんにお話しを伺い、設計の視点で「おにクル」ができるまでの経緯と、「おにクル」が茨木市もたらす変革について教えてもらいました。

市 川 雅 也 Masaya Ichikawa
1991年生まれ。豊田工業高等専門学校にて5年間建築設計を学び、立命館大学大学院にてランドスケープデザインを専攻。ランドスケープデザインと建築が融合した都市環境の創造を目標としている。2016年竹中工務店設計部に入社後、武庫川女子大学公江記念館、茨木市文化・子育て複合施設おにクルの設計を担当。TallinnArchitectureBiennale2022 国際アイデアコンペにて、資源循環と建築の連関をテーマにした提案で最優秀賞受賞。2021年より日本建築協会U35委員会に所属し、IBARAKISTREETACTION(社会実験)の企画・運営の他、遊牧民のように移動する木家具「ノマドギ」の開発などを行っている。現在、竹中工務店 大阪本店 設計部に所属。
「2コア1パーク」のまちづくりから誕生した「おにクル」
大阪府の北部に位置する茨木市。自然と都市が調和し、大阪や京都へアクセスしやすいことからファミリー層やオフィスワーカーに人気のベットタウンです。
中心市街地の東西には、JR茨木駅と阪急茨木市駅があり、その中間地点には市役所や元茨木川緑地などの公共空間があります。最近は立命館大学がキャンパスを新設するなど、大阪都市圏のなかでも注目のエリアです。
一方、この2駅の間で、まちを歩いて回遊する人が少ないことが課題のひとつでした。
そこで、まちに歩いて楽しい恒常的な賑わいを創出するため、2つの駅をコア、中央の公共空間をパークと捉え、2016年から「2コア1パーク」のまちづくりが進められています。

「2コア1パーク」のアンカーとして2023年11月に誕生したのが「おにクル」です。パークエリアにある市民会館跡地の利活用が検討され、市民が歩いて訪れたくなる公共施設を建てる計画がはじまりました。
市民が好きに過ごせる“立体公園”のようなソーシャルスペースが価値に
「おにクル」という施設名は6歳の市民が考案したもの。茨木市民なら誰もが知っているおなじみの童話に登場する鬼のキャラクター「茨木童子」にちなんで「怖い鬼さんでも訪れたくなるほど楽しい場所に」という願いが込められています。

敷地面積約1万500平米、地上7階建ての建物の中には、これまで茨木市に点在していたホールや図書館、子育て支援センター、プラネタリウムなどの機能を1箇所に集約。開放的な窓からたっぷりと光が降り注ぐ吹き抜けから、2階に 妊娠から出産・子育てまでの支援や各相談窓口をワンストップで提供する「こども支援センター」や子育てフリースペース「わっくる」などがあります。
「おにクル」の設計コンセプトは“日々何かが起こり、誰かと出会う”。「おにクル」をつくる段階で市川さんたち設計チームがまず大切にしたのは、芝生広場に面してランドスケープと建築が融合するような広々としたオープンスペースを確保することでした。

市川さん「私たちがつくりたかったのは、ひとりひとり好きな場所を選んで自由に過ごせる空間が積層した“立体公園”のような施設でした。そのためには豊かなオープンスペースを確保することが必要でした。
公共施設における市民のニーズって些細なことなんですよね。例えば、今日は元気いっぱいだから活発に運動したいとか、時間に余裕があるからただ友達と喋りたいとか、仕事で疲れたからリフレッシュしたいとか。
そんなひとりひとりの市民活動を支えられるよう、様々な用途に対応できるオープンスペースをしっかりとつくることがおにクルの価値になると考えました」
その思いを形にしたのが7階建ての建物を貫く「縦の道」です。

ホールやシェアオフィスなど機能が異なる施設を大きな吹き抜け空間でゆるやかにつなぎ、縦の道の周りには各階の用途に合わせた本を選書したライブラリーコーナーと読書スペースを配置。図書館が各階の用途をつなぎ、垣間見える各階の活動が、新しい出会いや発見を生む仕掛けとなっています。
オープンスペースがふんだんにあるように感じられる「おにクル」ですが、実は「おにクル」の共用部面積は35パーセントで、そのうちEVや階段、廊下などを除いた純粋なオープンスペースは9パーセントしかないのだとか。
市川さん「一般的な公共複合施設の共用部面積の割合は約35パーセントとされています。おにクルもまさに同じ条件で設計をしていて、共用部面積にゆとりがあるような与条件ではありませんでした。そのため異なる用途同士の機能を融通しあい、いかに<共用部“的”面積>を増やすことができるかがテーマでした。
例えば1階の多目的ホールは、壁が全面開放できる設計に。ホールで演奏会をやっている際に壁を解放すると施設全体が客席になり、ふらっと訪れた市民が演奏を楽しむことができます。また、一般のホールのホワイエ(待合)は使用時以外は立ち入れない空間となっていることが多いのですが、「おにクル」では普段は共用部として開放していて、ホール使用時には、カーテンで仕切ることで、ホワイエとしての機能を持たせます」

市民が「おにクル」を使いこなすための素地をつくる「暫定広場」
いくら良い建物をつくっても、使わなければ価値は発揮されません。「おにクル」の面白さは、施設が完成する4年も前から、茨木市役所の共創推進課によって市民が施設を使いこなすための素地を整えていた点にあると市川さんは語ります。
共創推進課は、市民が「おにクル」を使いこなすためのワークショップを計100回以上開催し、5,500時間以上の時間を市民との対話に費やしてきました。
市川さん「これらの目的は、市民ひとりひとりが自分ごととして関われる施設にするために、開館前から、「おにクル」にかかわる地域の人材を育てていくことです。そうすることで、初日から市民が使いこなせる状態をつくることができるんです。」
その中心となるのが「IBALAB@広場」という実験広場。市民会館跡地の北側に暫定広場を整備し、市民が「おにクル」を使いこなす”練習場”として活用されました。

中でも印象的だったのが、暫定広場でスケートボードをする市民との対話だといいます。
市川さん「市の職員は、スケートボードを禁止にするのではなく、『君たちが自分の居場所を守るために、どうしたら禁止にならないか一緒に考えよう』と声をかけました。
彼らは「IBALAB@広場」で活動する主体者が日々の課題を共有する『ひろばかいぎ』に参加し、他の利用者が多い時間帯を避ける、周辺への音の配慮するなど、自分以外の人が気持ちよく使えるルールを主体的に提案してくださいました」
そのほか「焚き火をしてみたい」「DJイベントを開催したい」など、普通なら規制されがちな提案もとにかくやってみる。どうしたらできるかを一緒に考えていく市民の姿勢が根付いていきます。
行政主導でルールを決めるのではなく、多様な活動を受け入れながら、市民とともに試行錯誤してルールをつくる過程そのものが「おにクル」のあり方を示しています。

ルールは使いながら変える“寛容さ”が居心地の良さに
開館後は、おにクルの“寛容さ”がさらに施設を利用しやすくしています。
市川さん「オープンして2週間目のとき、共創推進課がホールのホワイエエリアで盆踊りイベントを主催しました。上のフロアは図書館ですが、『図書館=静かに』といったパブリックイメージを壊し、利用者がお互いに寛容でいることを市民のみなさんにお伝えするだ機会になりました」
「おにクル」は色んな施設が集まった施設。図書館がありながら、イベントが行われることも、人が喋っていることも当たり前。開館直後にパブリックイメージを覆すメッセージを、しかもルールを決める側の茨木市役所が示していることに驚きます。

市川さん「1階と7階のみ飲食オッケーでしたが、結局みんな隠れて食べちゃったりして。そこまで問題が起きないとわかったので5・6階図書館エリア以外の全フロアで飲食可能になりました。
公共施設のルールってみんなが快適に過ごすために増えていくのが普通なんですけど、寛容な方に変えていくのも「おにクル」らしいと思います」
良い公共施設ができればまちや市民の暮らしが変わる
「おにクル」ができたことで市民の暮らしや周辺エリアにも徐々に変化が起こっているといいます。
市川さん「以前の茨木市は、ショッピングモールに車で出かけて、買い物や用事を済ませたら帰ってしまうライフスタイルが定着していました。しかし、「おにクル」には、徒歩や自転車で訪れる人もいます。「おにクル」が目的地となり、まちを歩いて楽しいと思える人が増えていくとうれしいですね」
「おにクル」を起点に人々の滞在と交流が生まれたことで、「おにクル」と茨木市役所を挟んだ車道の廃道化や、駅周辺の開発が計画されるなど「歩行者のために歩いて楽しい空間を増やそう」という機運が高まっています。


「良い空間、良い建築ができれば周辺も変わるはず」と話す市川さん。「おにクル」は市民活動の場であると同時に、市民主体のまちづくりを促進するきっかけとしても機能しています。
ワークショップ100回以上という途方もない対話を繰り返し、茨木市にふさわしい公共複合施設となった「おにクル」は「こんな暮らしがほしい」という願いを叶えていく場所へ。
市民が「自分たちのまちは自分たちでよくできる」と実感し、まちをより良くしようと動き出す。そんな社会変革の連鎖を「場のデザイン」で生んだまちのアンカー「おにクル」は、市民やまちの変化を支える空間であり続けます。
「おにクル」が生み出すイノベーションを、マチジカンではまたお伝えします。
Text:ココホレジャパン
Edit:橋岡佳令(竹中工務店)
「おにクル」のプロジェクト記事はこちら