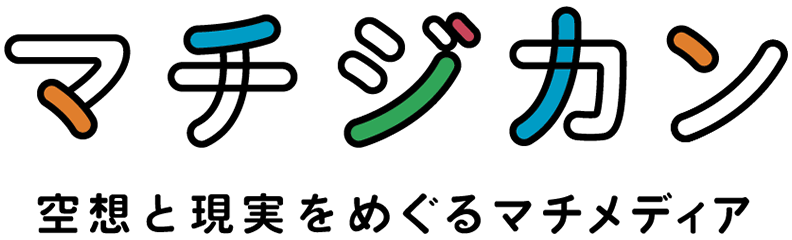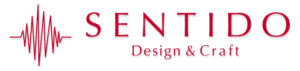都心から約1時間のところにある埼玉県比企郡小川町。荒川の上流部に位置し、町域の6割がスギヒノキの人工林と自然豊かな里山に囲まれ、約50年前から続く有機農業の聖地として知られています。
自然減を筆頭に人口減が課題となっていますが、東京とのアクセスの良さや、自然豊かな子育て環境、食や暮らしを自分たちで創りたいと、移住者が近年増えつつあります。
かつては長野や秩父から江戸に向かう途中の宿場町として栄えた歴史があり、ユネスコ無形文化遺産になっている和紙「細川紙」や絹織物、木建具を作る職人が住んでいたことから様々な産業が発展しました。
歴史的な建物も多く現存しており、料亭や食事処など従来の使われ方で残っている建物や、蔵や古民家をアトリエやカフェにリノベーションしているものも多くみられます。
このような自然または文化的な特長が京都と似ていることから、「全国京都会議」が認める「小京都」にも加盟しており、週末や観光シーズンには登山やまち歩きなどのアクティビティを楽しみに観光客が訪れます。

ポテンシャルが高い一方で、小川町は埼玉県の中で「消滅可能性都市」の上位に位置し、少子高齢化や人口減少などの課題や、それによる空き家問題、かつての主要産業の衰退など多くの地域課題を抱えています。
2019年には、小川町、 NPO法人あかりえ、竹中工務店の3者が地域連携協定を結び、100年後も続く未来を目指したまちづくりが行われています。
連携協定で掲げている5つの項目
- 森林資源を活用した地域活性化や関係人口の増加等に関すること
- 環境教育や啓発等に関すること
- 歴史的建物資源や文化資源等の活用に関すること
- 木質バイオマス発電やエネルギーの地産地消等に関すること
- 前各号に掲げるもののほか、森林グランドサイクルの推進、地域循環共生圏の構築及びSDGs(持続可能な開発目標)の達成に関すること

築100年の石蔵を新しい働き方の場へ「石蔵コワーキングロビーNESTo」
2019年の地域連携協定後に全世界で広まった新型コロナによって、小川町の課題が浮き彫りになります。
コロナ禍によって広まったリモートワークなどの「新しい働き方」によって、東京から絶妙な距離の小川町には、さらに移住やUターンなどの希望が増えていきます。一方で、そのような人々を受け入れるコワーキングスペースなどの施設は町内にはなく、町の課題となっていました。
このような町の課題を解決すべく、まちの中心地にあった関東最大級の大谷石造りの石蔵をリノベーションし、小川町の新しい交流拠点として生まれ変わらせるプロジェクト「コワーキング ロビーNESTo」の整備が始まりました。

築約100年の石蔵をこれからの100年も使い続けられるよう、2020年に「石蔵保存活用協議会」が設立されます。前述の地域連携協定の3者に、石蔵の所有者である三共織物株式会社を加えた4者が構成員となり、公的資金も活用しながらの計画を行っていきました。
計画・設計を小川町の設計事務所である「センティード株式会社」と、施工を小川町の工務店である「有限会社杉田工務店」の協力の元、限られた予算と工期の中で、地域の資源である石蔵を活かした新たな拠点整備を行うことになりました。
整備にあたっては、内装の木材はすべて町産木材とし、利用者の快適性を向上させると共に木材への興味関心のきっかけづくりをテーマに整備を行いました。
特にNESToのアイコンとなるスギの大テーブルは、樹齢約100年の町内のスギを伐採から行い、ワークテーブルとしても、イベント時のロングテーブルとしても使えるデザインとしました。
コワーキングだけではなく、町の催しやアートや音楽など様々なイベントに対応できるフレキシブルな空間となっており、週末には町内外の様々なイベントを行うことが可能となりました。

整備にあたって多くの課題がありながら、関係者の協力により2021年5月に「コワーキングロビーNESTo」として開業し、今では多くの町内外のワーカー達が訪れています。ホテルのような開放的なロビーがまちを楽しむ入口となり、“働く・憩う・集う”をテーマに町内外の人が有機的に交わる空間が広がっています。
場が人を呼び、人が集って新たなプロジェクトが生まれます。小川町は、都会に一番近い中山間地域のイノベーションタウンとして今後も注目していきたいと思います。
地域の資源や課題をともに体験することで、各企業の抱えている課題や新しい事業の在り方など、新たな気づきがみえてきます。